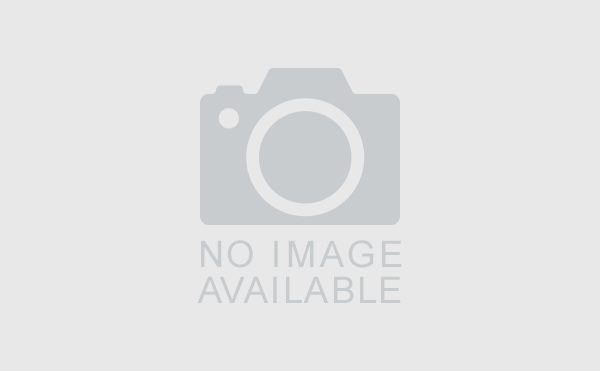心理学と精神医学
人の心というものを考える時に、いろいろな捉え方、研究の仕方があります。それが積み重なると学問としてノウハウが蓄積されていくわけですが、代表的なものに心理学と精神医学があります。他にも哲学や宗教学など心を問題にした学問はあるのですが、抽象的でない現実の心を扱う学問ではありません。(それはレベルの高低ではありません。どれも重要なものですがジャンルの違いです)
たぶん実際に学ばれた方や関わりの深い方以外では、心理学と精神医学の違いはわかりにくいものでしょう。精神医学の中の精神分析という単語を持ち出せば、もう一般の方には同じ物に見えてしまうのではないでしょうか。ですが、この二つは全く別の物なのです。よほど極端な学説以外では現在この二つを混同する立場はありません。
もちろん同じ対象を扱うわけですから、相互の交流や影響はあります。その大きな理由は片方の医学的な立場は極端な言い方をすれば「治ればいい」のです。何が正常で異常かの基準は別に論じますが、社会的に身体的に問題なく生きていけるのであれば、それは医学的な問題にはならないのです。
逆に心理学的な立場では正常か異常かの判断はあまり問題ではありません。いってみれば個体差です。心の理、つまり動くプロセスがどうなっているのか、何が起こっているのかを細かく見ることが心理学です。
これを書いている自分は心理学畑出身なのでイメージに偏りがあるかもしれませんが、心理学の人間は何かを治そうとか役立てようとしていることが少ないものです。そして心以外のことで本当は密接に絡み合っている物、例えば体や薬のことには本当に詳しくありません。そして、その影響を過小評価することもしばしばです。
では全ての心理学が役に立たないのかというと、そんなことはありません。ただすぐに応用がきくわけではない、ということです。心理学の中にも対象によってジャンル分けがされています。(老人、児童、対人、障害、等々)そして取り扱い方も色々です。(基礎、応用、実験、臨床、人文、等々)
実験心理学のデータと人間性心理学の教科書を同時に見れば「これが同じくくりの学問なのか?」といいたくなるでしょう。多岐にわたる、と言えば聞こえは良いですが、要するに心に関する基礎学問は全て心理学に入ってしまうのです。
わかりやすく例を挙げましょう。有名な精神分析のフロイトや弟子(これも捉え方次第ですが)のユングは二人とも医者です。犬の条件反射で有名なパブロフは生理学者で実験医学研究所を作りました。IQを計る知能検査で有名なビネーは心理学者、発達理論のピアジェも心理学畑です。
それぞれの立場や学問としての成り立ちは違うのですが、上手く棲み分けてきたとも言えます。ですが、やはり摩擦も生じます。日本では臨床心理士の国家資格化をめぐって、もう長い間論争があり、何度も計画、法整備は頓挫しています。
それぞれの言い分もわかります。心の専門家としてカウンセリングで心をのケアをする、という心理学の立場、その責任を負うのは医者ではないのか、という立場。この論争は「医者が既得権益を守っているだけじゃないのか」という見方をされることもありますが、そんなレベルの問題だけではないことに注意が必要です。
確かに心理学というのは発生の歴史から応用の部分も含めて「実際に責任を持ってその技法を使う」という部分を軽く見ていた経緯があります。(もちろん近年多くの人が取り組み改善されてきているのですが)
昔のように心の基礎研究の心理学と実践応用の精神医学に棲み分けをするには、もう学際的に分野がクロスオーバーしすぎているのでしょう。それに時代や社会制度のニーズも考えなければなりません。これを読む方も「心を癒してくれるなら資格や経歴は何でもいい」とは言わずに、双方の言い分に耳を傾けてみてはいかがでしょうか。