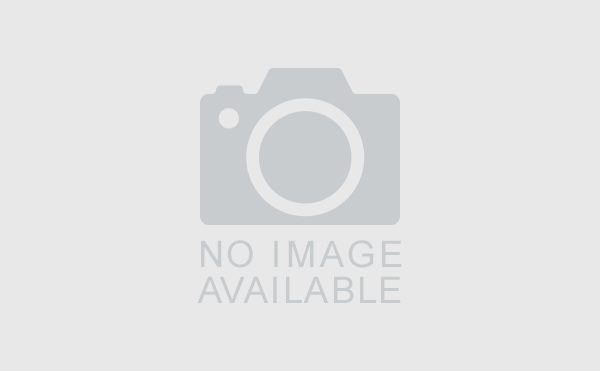精神病、精神疾患、精神障害という言葉
難しい分類自体ではなく言葉の話題です。精神病という言葉を聞くと、その分野に縁のない人は大抵ビックリ、というより重大な触れてはいけない話題のような気がしてしまうこともあるでしょう。
もちろん病気ですから軽い話題ではないですし、面白半分にする話題でもないのですが、多くの場合イメージ先行で誤解と共に広まり、話題にしにくいこともあって間違いやオーバーな部分があっても訂正される機会が少ないために困る部分があります。
言葉の定義は難しいものですが、精神病という言葉は一般的な意味で言えば心の病気全般、特に酷い症状のものを指すことが多いでしょう。ではきちんとした医学的な定義を見てみましょう。
よく使われるものにICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類の第十版)とDSM-IV-TR(精神障害の診断と統計の手引きの第四版のテキストリビジョン)があります。両者とも現在の版が出てかなりたっており改訂作業中で、近年改訂版のICD-11とDSM-Vが発行予定です。若干定義が変わるかもしれませんね。
現在この二つでは精神病にあたるものは「精神病性障害」と表現されて、一般的な感覚とは違い気分障害や癲癇、不安障害などを含まない分類です。また難しいことに日本の従来の分類では、これとも違う分類になっています。(これは他の国でもある問題のようです)
分類することに意味があるのか?という疑問もあるでしょうが、治療を行ったり本人や周囲が病気と向き合うためには、まずその本質をつかむことが重要になります。ただ分類には注意が必要です。それが「原因」による分類なのか「結果、症状」による分類なのかで違うからです。
症状自体では幻覚、幻聴や妄想、不安、恐怖感などが思い浮かびますが、原因というのは何でしょう。ここが一番誤解を招きやすい部分です。それは原因には様々な要因が絡み合っている、ということです。
大きく分けると心因性、外因性、内因性ということになります。心因性というのは文字通り心が強いストレスやショックを受けることが原因になるものです。外因性というのは原因が非心因性、つまり心以外の脳や神経、外傷などによって引き起こされるものです。内因性というのは未だ原因がはっきりしないが脳の中にその原因があると推測されているものです。内と外の概念が少しややこしいので注意してください。
その他に環境因というものを考える場合がありますが、注意するべきはこれらの原因がはっきり特定できるものもあれば、複数の原因が絡み合っている場合もある、ということです。そしてその分類はあくまで原因であって症状ではないということです。
では社会通念で今まで精神病と呼んでいたようなカテゴリーはどうなるのかというと、精神疾患という言葉があります。ただこれも全く昔でいう精神病と同じ範囲だというわけではありません。しかし統合失調症や躁鬱病、パニック障害、適応障害のようなものまで含むので、ほとんどの人の「心の病」のイメージと近いものだと思います。
この文章で伝えたかったことは、「心に関する言葉の定義は時代と共に変わる」「分類することは大事だが原因の分類と症状の分類は異なる」ということです。このサイトでは言葉の定義に十分注意を払うつもりですが、定義自体の揺れが存在するため引用や参考には注意してください。